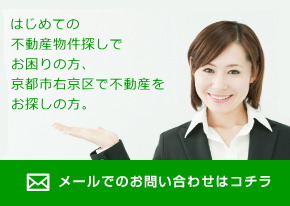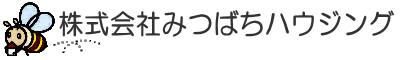暇は価値を生んだ
小学校低学年の頃、私は明らかに学校嫌いだった。幸運なことに? 私はお腹は丈夫だったが呼吸器は弱かった。冬にはよく風邪をひいた。今日は学校を休めるということは、私にとって幸いな日だった。
その上、そういう日には母が本を1冊買ってくれた。「風邪をひいたご褒美」と母ははっきり言ったが、私は学問的な性格ではなかった。
江戸川乱歩や大下宇陀児の推理小説を1冊買ってもらうと、私はニコニコして再び蒲団(ふとん)にもぐり込んだ。
私は明らかに学校に行くのが嫌いで、家にいるのが好きな子だった。しかし今の人たちは大人も子供もそうではないらしい。彼らは明らかに外に行けない状態が発生することを恐れて問題にしている。
彼らはコロナを恐れているというより、家から外に出ないことを恐れている。外へ出られないと米や醬油(しょうゆ)がなくなるわけではない。都会では、100メートルも歩けばインスタント食品や缶詰を売っている店も自動販売機もある。2日や3日自宅に籠城するくらいの食べものは、今の時代誰でも手に入れられる。それなのに外出ができないことを恐れるのである。
家に落ち着ける自分の部屋がないからだ、という説明をする人もいる。確かにそういう場合もあるだろう。しかし昔の学生は3畳1間が自分の部屋だという人も珍しくなかった。万年床に入って本を読む分には、10畳だろうと3畳だろうと大した違いはない。
しかし問題は、3畳では1日家にいるのがむずかしいと感じる事が、世間に認められそうになってきていることだ。
今は休みは外出するもの、と人々は決めているようだ。しかし昔、休みに人々は家にいた。怠け者は一日中、ごろごろ寝そべって本を読んでいた。体は休まるし、頭に知識は増える。おまけに外に出ることで、余計な小遣いをつかわなくて済む。
むしろ現代の生活で問題になるのは、寝そべる時間や本を読む暇がないことなのだ。しかし外界や他者と「密な」時間や距離で生きる危険性は、ほとんど誰も気にしない。
時間は、いつも変化に富み、他人にもその使い方を説明できるようなものでなければならない、と今の人々は考えている。昔、学生の生活では、することが全くない時間がいっぱいあった。本当は学問をするための時間であったのだが、学問はしたくなかったのである。
しかし遊ぶには、小遣いが足りなかった。だから若者は、止やむなく家で寝そべって古本を読んだり、妄想に近いことを考えたりして時間つぶしをしていたのだ。しかしこの妄想が、時には未来に創造的な世界を生み出す力を持つことがあった。明らかな暇は、決して不毛なものではない。それはあらゆる世界を創造し得る豊饒(ほうじょう)な大地だったのである。
暇は、暇だから価値を生めたのだ。それを簡単に説明可能な使い方で、軽々に埋めてはならない。遊園地やデパートの人ごみの写真を見ると、その不思議な力関係を思い出す。
(曽野 綾子/文春文庫)
良い文章ですね。
海外では仕事の合間の昼寝や長期バカンスが当たり前の国民性の国が存在します。
国によっては働く人はメチャクチャ働くお国柄もあるようですが。

新型コロナ禍を経て、遊び方や趣味の時間の過ごし方、働く意味や意義も随分変化したなと感じてます。
それはお家探しをされているお客様にも顕著に表れていますし。
今年のGWは何処へ行こうかな!?」って・・・上の文章読んだんかいっ(笑)
嵐山こども食堂ホームページ→http://arashiyamakodomosy.wix.com/kodomosyokudou
嵐山こども食堂Facebookページ→https://www.facebook.com/arashiyama.kodomosyokudou/
嵐山こども食堂Instagramページ→https://www.instagram.com/arashiyamakodomo/
京都市右京区の名所・旧跡・美味しいケーキ・美味しいお菓子やご近所の名店・グルメ情報・HPの無いお店もたっぷり登場させて行きます!

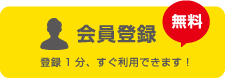




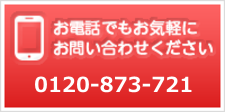
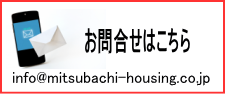
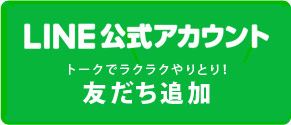
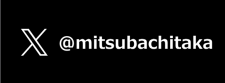

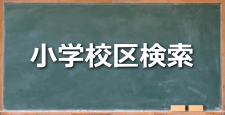
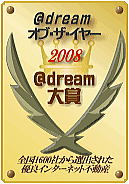

 ・売買会員ログイン
・売買会員ログイン